グリーンの法則
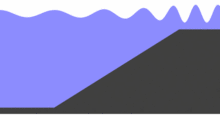
グリーンの法則(英語: Green's law)は、19世紀のイギリスの物理学者、ジョージ・グリーンが提唱した、津波の波高と水深との関係を表す法則である。端的に言えば「水深が浅くなると津波の高さは高くなる」という法則である。
概要
この法則は次の式で表される[1]。
この時、Hは波高、hは水深、bは波面に垂直で相隣りあう一組の波高線の幅である。添え字(0と1)は、それぞれ波源域の縁と海岸付近によるものを示す[1]。
脚注
- ^ a b "グリーンの法則". 法則の辞典. コトバンクより2022年2月27日閲覧。
関連項目
- 表示
- 編集







